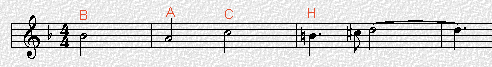
マタイ受難曲の謎
このページに記載の内容は、著者しんのすけ個人の意見であり、
BENの活動内容とは全く無関係であることをご承知下さい。
皆さんは、バッハが自分の作品中にサインを残していることをご存じでしょうか。
その一つに、BACHの各アルファベットが音名にあることを利用し、
その音型をサインとして示していることが知られています。
前に私が見た東独作製のバッハの伝記映画では、バッハが口笛でBACHのメロディを吹いて、
奥さんに帰宅を知らせる場面がありました。
例えばフーガの技法では、
バッハが絶筆する前の第3のフーガ主題としてBACHの音型が使われています。
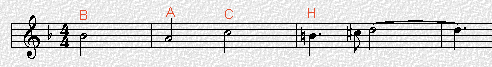
またモーツァルトもバッハに敬意を表したのでしょうか、
レクイエムのラクリモーサの第7小節のバスパートにBACHが使われています。
二人とも絶筆の部分にBACHを用いているのは大きな謎ですね。
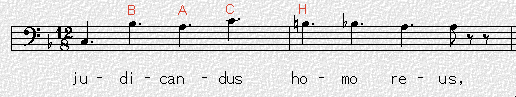
バッハは、まれにBACHを反転したHCABを使うこともあります。
マタイ受難曲では、第23曲の間奏部分にはっきりとHCABがあります。
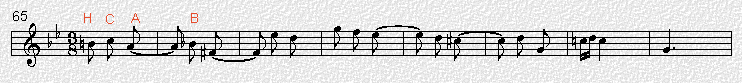
もう一つのサインとして、14の数が有名です。
アルファベットの順番に番号を付けると、B=2、A=1、C=3、H=8となり、その合計が14となります。
バッハはこの数を好み、何かメッセージを伝えたい部分に使っています。
例えばマタイ受難曲では、
イエスが死んで地震が起きた後の第63b曲のバスパートの音の数が14個です。
これはバッハ自身も「まことに、この人は神であった」と叫んでいることを示しています。
また第42曲のバスアリアにおける主題の音の数も14個です。
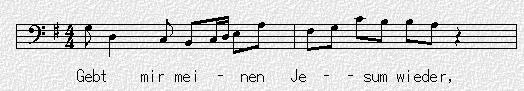
このように通奏低音やバスパートにバッハのサインが多く見られることから、
私はバッハの声域はバスであったと考えています。
さて、マタイ受難曲にはもう一つのサインがあることが知られています。
それは、頻繁に歌われる受難コラールの最初の音型、移動度読みでミラソファミレミです。
マタイ受難曲にはこの音型そのもの、あるいはこの音型が変化した音型がたくさん現れることから、
バッハはこの音型をマタイ受難曲の作曲の土台としている、と私は考えます。
例えば第39曲の有名なアルトアリアの通奏低音に
はっきりと現れていることは、多くのバッハ学者も指摘しています。
なお最初の「ミ」の音はヴァイオリンの最初にあります。
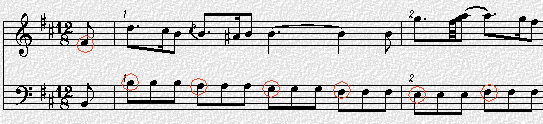
はっきりそれとわかる部分が
第23曲バスアリアにもたくさんあります。
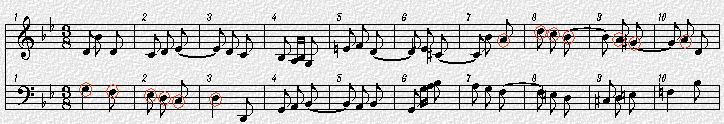
第35曲テノールアリアの
ヴィオラ・ダ・ガンバの最初にもあります。
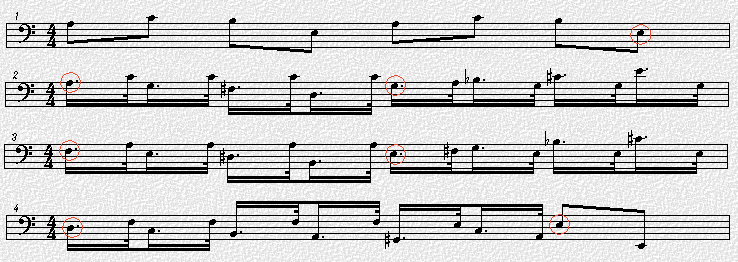
第57曲バスアリアの通奏低音、これもそうでしょう。
「ミ」の音はヴィオラ・ダ・ガンバのアウフタクトにあります。
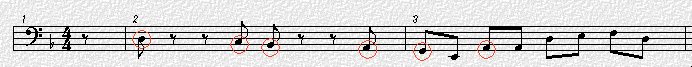
第6曲アルトアリアの通奏低音、これもそうみたいです。
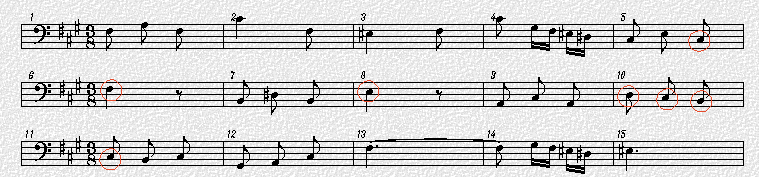
少々崩れていますが第65曲バスアリアの通奏低音
「ミ」の音はオーボエ・ダ・カッチャの最初の音にあります。
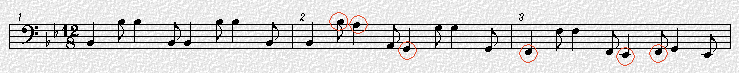
第13曲ソプラノアリアでは、ソプラノ独唱の最初に現れます。
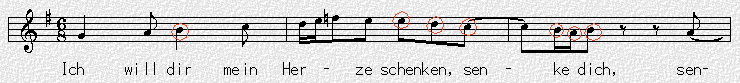
第20曲テノールアリアでは通奏低音の第5小節からと
合唱のソプラノパートの第52小節からにあります。
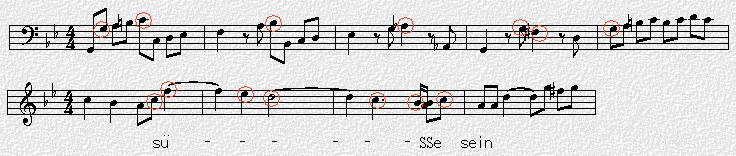
第27a曲アリアのテーマもそうでしょう。
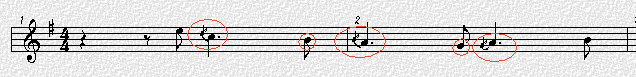
第42曲バスアリアの前奏にもあります。
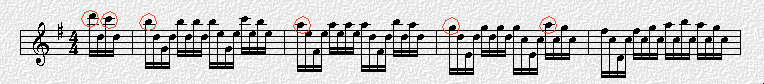
アリアだけではありません。
例えば第1曲合唱の二つのテーマにあります。
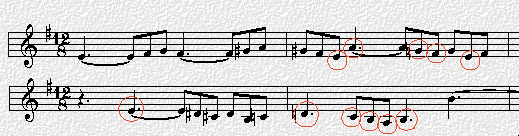
第45b,50b曲の「十字架につけろ」の合唱では、
かなり変化していますが、同じ音型がテーマにあります。
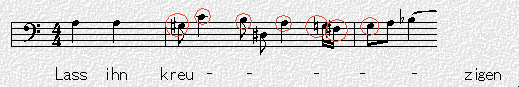
第63b曲合唱では、ソプラノとベースに分割されて現れます。
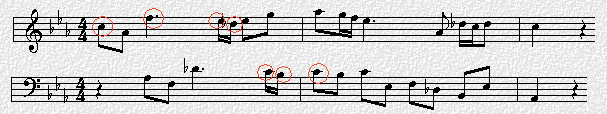
また第68曲終曲の最後の小節で、わざわざ不協和音のHの音を、
しかも1オクターブ上げてフルートに入れたのは、なぜでしょう。
HCと続くように名前の一部を入れたとも考えられますが、
その前の小節からつなげてこの音型を作っていることを
強調したかったのではないかと私は思います。
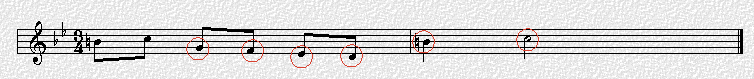
他の曲にもそれらしい部分はたくさんあるのですが、
この音型のことはこれくらいにして、そろそろ本題に入りましょう。
マタイ受難曲の楽譜を眺めていたところ、
上の三つのサインのうち二つが連続して現れているところを発見しました。
第23曲です。もう一度その部分を見てみましょう。
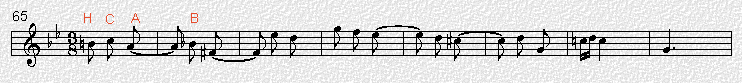
HCABに続く音符の数が14個です。タイは二つの音符で一つと数えます。
また、この曲には、前に述べたように、
ミラソファミレミの音型のサインもたくさんあります。
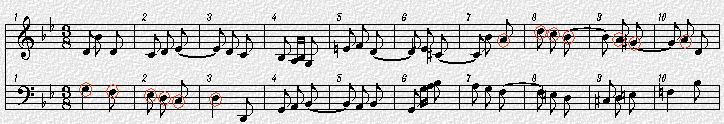
ミラソファミレミの音型がこの曲中に何回出てくるか数えたところ、あやしい部分を省くと14個ありました。
となると、バッハはこの曲に3種類のサインをちりばめ、きわめて重きを置いていたように思われます。
HCABは第65小節にあります。65という数に何か意味があるのでしょうか。
バッハはバス声部を重要視していることから、他のバスアリアの曲を見てみます。
先ず第65曲のバスアリア、これを聞くと長いマタイ受難曲ももうすぐ終わりで、
やれやれという気持ちと、もう終わりかという気持ちが入り交じった複雑な気持ちになりますね。
第65曲の第65小節からは、「begraben(葬る)」のメリスマが始まり、
このメリスマには、少し崩れていますがミラソファミレミの音型が見られます。
つまりこの曲でも、第23曲と同様に
バッハのサインと65が密接に結びついているのです。
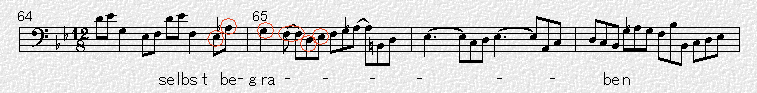
また第42曲のバスアリアは、第65小節で終わっています。
この曲にも、先に述べたように14の数とミラソファミレミの音型があり、
やはりバッハのサインと65が密接に結びついています。
65という数とバッハを結びつけるものは何でしょうか。そうです。亡くなった時のバッハの年齢です。
そうすると、このように無謀な仮説が生まれます。
ここからは、私の荒唐無稽な仮説ですので、眉に唾を付けてお読み下さい。
「バッハは、自分が何歳で死ぬかを知っていた!」
第65小節から始まる「begraben(葬る)」のメリスマは、いかにも象徴的です。
そしてこの曲で初めて「begraben(葬る)」が出てくるのは、第14小節です。
また「Ich will Jesum selbst begraben(私はイエスを自ら葬りましょう)」というフレーズの14番目の音には
「selbst(自ら)」が付けられています。
しかも、「selbst begraben」は、この曲中に14回出て来ます。
こうなると、このように考えざるを得ません。
「Ich will Jesum selbst begraben(私はイエスを自ら葬りましょう)」という歌詞に
、バッハは自らの死を重ねて見ていたのです。
けれども生きてマタイ受難曲を作曲しているバッハに、自分が死ぬ歳などわかっていたはずがありません。
そこを敢えて、バッハは自分の死期を予知していたと考えると、さらに次の仮説が生まれます。
マタイ受難曲中に生まれた年(1685)と没した年(1750)のサインがあるのではないか、という。
そこで小節数を数えてみました。最初から1685小節目は、ちょうど第40曲のコラールの第1小節でした。
そして1750小節目は、第42曲バスアリアの第15小節でした。(数え間違いがなければ・・)
第40曲のコラールはペテロの否認の場面を閉じるコラールなのに、歌詞が場面としっくりこないことを
以前より不思議に思っていました。その歌詞は以下のとおりです。
40.Choral 40.コラール Bin ich gleich von dir gewichen, たとえ私があなたから離れたとしても Stell ich mich doch wieder ein; 私はきっと再び戻ってきます。 Hat uns doch dein Sohn verglichen 神の御子は私達を、 Durch sein Angst und Todespein. 苦悩と死の痛みであがなって下さったのです。 Ich verleugne nicht die Schuld, 私は、わが罪を否定しません。 Aber deine Gnad und Huld しかしあなたの恵みと愛は、 Ist viel grosser als die Sunde, 私のうちにある罪の深さより Die ich stets in mir befinde. はるかに大きいのです。
第41曲では、ユダがイエスを売った代償の銀貨30枚を返し、後悔して首をつって死んだことが語られます。
そして第42曲では、バスソリストが「イエスを返せ、見よ、放蕩息子が人殺しの報酬の金を投げ返したのだから」
と歌います。この曲はユダが歌っていると解するのが自然ですが、死んだユダが歌うのはおかしいという説もあり、
決定説は今のところないようです。
第42曲の第13~14小節には、前に述べたように14の音があり、
その次の小節が1750小節目です。
そこには「gebt mir, meinen Jesum wieder(私のイエスをもう一度私に与えよ)」という
第13~14小節と同じ歌詞が繰り返され、「gebt mir」という命令形で始まっています。
誕生の時が第40曲、没する時が第42曲、それらの歌詞は上のとおりですから、
そこから得られる仮説は次のようになるでしょう。
バッハは自らの人生を振り返って罪の深さを知り、
自分をユダにたとえて、死ぬ際にはイエスを求めようとするであろうことを
マタイ受難曲の中で告白しているのではないか、と。
お読みいただき、ありがとうございました。
これに対する反論など、お聞かせいただけると嬉しいです。
しんのすけ@BEC
2000年9月3日